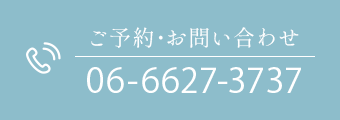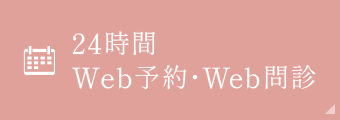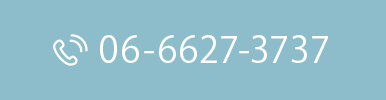息切れするのはなぜ?
 階段や坂道をのぼると息切れがする、または歩くだけで息切れがする場合、心疾患や肺疾患が原因となっている可能性があります。よく「どこからが病的な息切れですか?」と質問されることがありますが心肺機能が高い若い方と中高年の方では基準が異なります。基本的には、「以前は特に問題なかった運動で息切れがする」「息切れに加えて他の症状もある」といった場合には病的な息切れを疑い、早めに当院にご相談いただくことをお勧めします。
階段や坂道をのぼると息切れがする、または歩くだけで息切れがする場合、心疾患や肺疾患が原因となっている可能性があります。よく「どこからが病的な息切れですか?」と質問されることがありますが心肺機能が高い若い方と中高年の方では基準が異なります。基本的には、「以前は特に問題なかった運動で息切れがする」「息切れに加えて他の症状もある」といった場合には病的な息切れを疑い、早めに当院にご相談いただくことをお勧めします。
息切れの症状とその背景
息切れは、身体がより多くの酸素を取り込もうとする反応です。身体全体の臓器の酸素不足、もしくは酸素の利用障害によって引き起こされます。身体に取り込んだ酸素は、全身の臓器へと運ばれ、各細胞で利用されます。肺や心臓だけでなく、血液・筋肉などもかかわっているため、息切れを起こす原因は多岐にわたります。病気以外では、加齢や長期間の運動不足、安静による心肺機能や筋力の低下も原因となります。
息切れの症状チェック
息切れを評価する基準に、「MRC 息切れスケール(Modified Medical Research Council Dyspnea Scale, mMRC)」というものがあります。
グレード0
激しい運動時にのみ息切れを感じる
グレード1
平地歩行では息切れしないが、坂道や階段では息切れを感じる
グレード2
平地歩行でも同年代より遅れるか、息切れのため立ち止まる必要がある
グレード3
100m程度(または数分間)の歩行でも息切れのため立ち止まる
グレード4
家を出られない、または衣服の着脱時にも息切れを感じる
mMRC2以上の場合、医療機関の受診が必要となります。特にmMRC3以上かつ急性増悪の徴候(急激な息切れの悪化、安静時でも息苦しさを訴える、労作時の呼吸困難が著明に増悪し日常生活が困難など)がある場合は、入院を積極的に検討します。
息切れを起こす心臓の病気
息切れを伴う代表的な心臓の病気をご紹介します。心臓は血液を全身へ送り出すポンプの役割を担っています。心臓の機能が低下すると、必要な酸素を十分に供給できなくなり、身体は酸素を補おうとして呼吸を速めるため、息切れが生じます。
心不全
心不全とは、心筋梗塞や心臓弁膜症などの疾患によって心臓が全身へ血液を送り出す「ポンプ機能」が低下した状態を指します。この機能が低下すると、全身に十分な血液が行き渡らなくなり、他の臓器にも影響が及びます。その結果、動悸・息切れ・呼吸困難・むくみ・疲労感など、さまざまな症状が現れます。
心臓弁膜症
心臓には、右心房・右心室・左心房・左心室という4つの部屋があり、この部屋の中を血液が順番に通っていきます。心臓弁膜症とは、これらの部屋のあいだに存在する「弁」が障害され、血液の流れが正常でなくなる病気です。単に「弁膜症」と呼ばれることもあります。
初期は症状が現れないことが多いのですが、病状が進行すると息切れ、動悸、むくみなどの心不全症状が現れます。
虚血性心疾患
(狭心症・心筋梗塞)
心臓は全身に血液を送るポンプの役割をしていますが、自分自身も血液を必要とします。心臓に酸素や栄養を届ける血管を「冠動脈」といいます。通常、運動などで心臓が活発に動くと、冠動脈の血流も増えて心臓に十分な酸素が供給されます。ところが、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が原因で動脈硬化が進むと、冠動脈が狭くなったり詰まったりして、血流が不足することがあります。冠動脈が狭くなり、一時的に血流が不足する「狭心症」、冠動脈が完全に詰まり、心筋が壊死してしまう「心筋梗塞」。これらをまとめて「虚血性心疾患」と呼びます。どちらも胸痛や圧迫感、息切れなどの症状を伴います。特に心筋梗塞は命に関わることがあるため、強い胸痛や冷や汗、吐き気などがある場合はすぐに救急車を呼ぶことが重要です。また、狭心症の発作を経験した場合も、早めに循環器内科を受診しましょう。
不整脈
脈拍が速くなる、遅くなる、飛ぶ・リズムが乱れるといった状態を指します。通常、心筋は電気信号によって規則的に収縮と弛緩を繰り返していますが、何らかの原因によってこの電気信号が乱れると、不整脈が起こります。脈拍が速くなるものを頻脈、遅くなるものを徐脈とよび、飛ぶ・リズムが乱れるものには期外収縮、心房細動などの疾患があります。症状としては、動悸・息切れ、胸の不快感、めまいなどが挙げられます。重症例では、意識を失ったり、突然死を引き起こしたりすることもあります。
息切れを起こす呼吸器の病気
肺などの呼吸器は主に、酸素を血液中に取り込む役割を担っています。呼吸器の病気があると、血液中に酸素を十分に取り込めず、全身の臓器に十分な酸素が行き渡らなくなるため、息切れが生じます。急に息切れが起こる場合には気管支喘息や肺炎が、慢性的に息切れが続く場合には慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの可能性が疑われます。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
COPDは主に喫煙が原因で発症する病気です。長年の喫煙により、気管支に慢性的な炎症が起こったり、肺の弾力が低下したりすることで、息切れや咳などの症状が現れます。進行すると、最終的に呼吸不全に至ることもあります。また、COPDの患者さんが風邪やインフルエンザにかかると、症状が悪化しやすく、重症化のリスクが高まります。そのため、禁煙や予防接種(インフルエンザ・肺炎球菌ワクチン)が重要です。
気管支喘息
気管支喘息は、アレルギーによる慢性的な気管支の炎症によって、気道が狭くなり、呼吸がしづらくなる病気です。発作を起こすと、ゼイゼイ、ヒューヒューという特徴的な呼吸(喘鳴)、呼吸困難、咳(特に夜間や早朝に悪化しやすい)などの症状が現れます。
肺炎
肺炎は、細菌やウイルスが肺の肺胞に入り込み、炎症を引き起こす病気です。肺胞で感染が進行すると、酸素と二酸化炭素の交換がうまくいかなくなり、息切れや呼吸困難が現れます。また、咳、痰、発熱、胸痛などの症状も伴うことがあります。肺炎は早期に適切な治療を行うことが重要で、特に高齢者や免疫力が低下している人では、重症化するリスクが高いため、早期受診が必要です。
心臓・呼吸器以外の息切れを起こす疾患
息切れは心臓や呼吸器の疾患だけでなく、貧血や神経筋疾患などが原因となることもあります。また、不安やストレスの影響によって、一時的に息切れが起こりやすくなるとういこともあります。
息切れの治療
 息切れを改善するには、その原因疾患に応じた治療を行います。呼吸器疾患や心臓疾患の場合、薬物療法などの内科的治療が行われます。また、禁煙、適度な運動、栄養バランスの良い食事、ストレスの解消といった、生活習慣の改善も大切です。息切れの原因によっては、リハビリテーション、呼吸器トレーニングも必要になります。
息切れを改善するには、その原因疾患に応じた治療を行います。呼吸器疾患や心臓疾患の場合、薬物療法などの内科的治療が行われます。また、禁煙、適度な運動、栄養バランスの良い食事、ストレスの解消といった、生活習慣の改善も大切です。息切れの原因によっては、リハビリテーション、呼吸器トレーニングも必要になります。
息切れが起きた時の対処法
 息切れが起きた時には、安静にすることで改善が期待できます。ただ、病状と相談しながら適度な運動を行うことは、長期的に考えると息切れなどの症状の改善につながるため、医師と相談してできるだけ継続しましょう。ウォーキングや軽いストレッチがおすすめです。深呼吸や腹式呼吸も有効です。酸素を多く取り込むことで、息切れの改善が期待できます。鼻からゆっくり息を吸い、お腹を膨らませるように意識しながら呼吸をしてみてください。また、姿勢も大切です。胸を張るよりも、やや前かがみになっている時の方が、呼吸が楽になります。テーブルや膝に手をついて支えると楽になります。息切れの予防という意味では、生活習慣の改善が大切です。バランスの良い食事・適度な運動・十分な睡眠によって、身体の調子を整えましょう。アルコール、自律神経を刺激するコーヒーなどのカフェイン入り飲料は、摂り過ぎないようにしてください。また喫煙をしている方は、禁煙をしてください。
息切れが起きた時には、安静にすることで改善が期待できます。ただ、病状と相談しながら適度な運動を行うことは、長期的に考えると息切れなどの症状の改善につながるため、医師と相談してできるだけ継続しましょう。ウォーキングや軽いストレッチがおすすめです。深呼吸や腹式呼吸も有効です。酸素を多く取り込むことで、息切れの改善が期待できます。鼻からゆっくり息を吸い、お腹を膨らませるように意識しながら呼吸をしてみてください。また、姿勢も大切です。胸を張るよりも、やや前かがみになっている時の方が、呼吸が楽になります。テーブルや膝に手をついて支えると楽になります。息切れの予防という意味では、生活習慣の改善が大切です。バランスの良い食事・適度な運動・十分な睡眠によって、身体の調子を整えましょう。アルコール、自律神経を刺激するコーヒーなどのカフェイン入り飲料は、摂り過ぎないようにしてください。また喫煙をしている方は、禁煙をしてください。