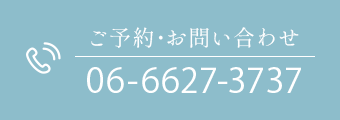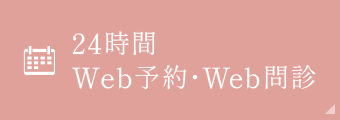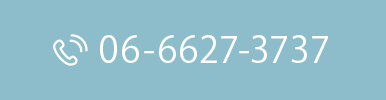- 睡眠時無呼吸症候群とは?
- 睡眠時無呼吸症候群の主な症状
- 睡眠時無呼吸症候群の症状の重症度
- 睡眠時無呼吸症候群の原因・
リスク要因 - 睡眠時無呼吸症候群の診断方法と
検査内容 - 睡眠時無呼吸症候群の治療方法
- 睡眠時無呼吸症候群を放っておくと
どうなる?
睡眠時無呼吸症候群とは?
日本人の約10人に一人が
睡眠時無呼吸症候群?
 睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に繰り返し無呼吸を繰り返す病気です。10秒以上の無呼吸が1時間あたり5回以上、または7時間あたり30回以上ある場合、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。現在、未受診の方を含めた潜在患者は、国民の10人に1人にものぼると言われています。いびき、日中の眠気といったよく知られた症状以外にも、気になる症状があれば、お早めに当院にご相談ください。
睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に繰り返し無呼吸を繰り返す病気です。10秒以上の無呼吸が1時間あたり5回以上、または7時間あたり30回以上ある場合、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。現在、未受診の方を含めた潜在患者は、国民の10人に1人にものぼると言われています。いびき、日中の眠気といったよく知られた症状以外にも、気になる症状があれば、お早めに当院にご相談ください。
睡眠時無呼吸症候群が
引き起こすリスク
睡眠時無呼吸症候群を放置していると、高血圧や糖尿病、心疾患、脳卒中などの発症リスクが高まります。また、日中にひどい眠気や集中力低下といった症状が引き起こされるため、仕事上のミス、居眠り運転による交通事故などのリスクも高まります。睡眠時無呼吸症候群は、健康、そして時に命を危険にさらす病気です。
睡眠時無呼吸症候群の主な症状

夜間に見られる症状
- いびきをかく
- 睡眠中の無呼吸
- 息苦しさで目が覚める
- 夜中に何度も目が覚める
- 寝汗をかく
- 家族にいびき、無呼吸を指摘された
日中に現れる症状
- 起床時の頭痛、熟睡感のなさ
- 強い眠気、居眠り
- 倦怠感
- 集中力の低下
- 記憶力の低下
- やる気が出ない
- イライラする
- 性欲減退
- ED(勃起不全)
睡眠時無呼吸症候群の症状の
重症度
睡眠時無呼吸症候群の重症度は、「AHI(Apnea Hypopnea Index)」に基づいて分類されます。AHIとは、睡眠1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数です。
| AHI | 重症度 |
|---|---|
| 5未満 | 正常 |
| 5以上15未満 | 軽症 |
| 15以上30未満 | 中等症 |
| 30以上 | 重症 |
重症度が高いほど、夜間・日中の症状が強く現れます。また、合併症のリスクが高まります。
睡眠時無呼吸症候群の
原因・リスク要因
睡眠時無呼吸症候群の原因
睡眠時無呼吸症候群は大きく、閉塞性睡眠時無呼吸症候群と、中枢性睡眠時無呼吸症候群に分けられ、それぞれ原因が異なります。
閉塞性睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群のうち、ほとんどがこの閉塞性睡眠時無呼吸症候群に分類されます。
気道(空気の通り道)が狭くなることで、無呼吸になります。
原因としては、肥満(特に首回りの脂肪の蓄積)、扁桃肥大、舌が大きい、下顎が小さい等が挙げられます。
中枢性睡眠時無呼吸症候群
気道が狭くなることはないものの、脳からの呼吸指令が適切に出されないことによって発生する睡眠時無呼吸症候群を中枢性睡眠時無呼吸と呼びます。主な原因として、甲状腺機能低下症、心不全、脳幹梗塞、脳炎、オピオイドの副作用などが挙げられます。これらの疾患や薬剤の影響により、脳の呼吸中枢が正常に機能しなくなることで、無呼吸が引き起こされます。
リスク要因
男性
睡眠時無呼吸症候群は、女性よりも男性に起こりやすい病気です。この性差は、男性の首回りに脂肪がつきやすいことが影響しているものと思われます。
生活習慣
喫煙、飲酒は、睡眠時無呼吸症候群のリスクを高めます。適度な飲酒は寝つきをよくしますが、睡眠の質を低下させ、夜間の中途覚醒が起こりやすくなります。
体格・骨格
太っている人、首や顔の脂肪が多い人は、気道が狭くなりがちで、睡眠時無呼吸症候群のリスクが高くなります。
また、もともと舌が大きい人、下あごが小さい(引っ込んでいる)人、扁桃・アデノイド肥大がある人も、同様に気道が狭くなりやすいと言えます。
睡眠時無呼吸症候群の
診断方法と検査内容
睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合には、一般的に以下のような検査を行い、診断します。
問診・ESS(睡眠尺度評価)
問診では、無呼吸やいびきの自覚・家族から指摘を受けたか、他の症状の有無、既往歴、服用中の薬などについてお尋ねします。
また、日中の眠気が病的なものであるかどうかを判断するため、簡単な質問票(ESS)を使用します。
睡眠時無呼吸症候群の疑いが少しでも残る場合には、簡易型ポリソムノグラフィ検査へと進みます。
スクリーニング検査
パルスオキシメータを指先につけ、普段通りに就寝していただきます。無呼吸によって起こる酸素の低下を検出します。ご自宅で受けていただける検査です。
簡易型ポリソムノグラフィー検査
指先と鼻にセンサーをつけ、普段通りに就寝していただきます。血液中の酸素、呼吸状態を確認し、睡眠中の無呼吸の有無、重症度を判定します。無呼吸の時間や回数も分かります。ご自宅で受けていただける検査です。
精密検査(ポリソムノグラフィー検査)
血液中の酸素、呼吸状態に加えて、筋電図・心電図・脳波などを調べる検査です。無呼吸の長さや回数、睡眠時無呼吸症候群の種類(閉塞性/中枢性)、睡眠の質、不整脈の有無、他の睡眠障害の有無などが診断できます。基本的に、病院など専門の施設に1泊入院をして行われる検査となります。
睡眠時無呼吸症候群の治療方法
睡眠時無呼吸症候群の治療方法には、以下のようなものがあります。
CPAP療法
(持続陽圧呼吸療法)
 CPAP(持続陽圧呼吸療法)は、睡眠時無呼吸症候群の治療で最も一般的な方法です。装置から伸びるホースの先に取り付けられたマスクを装着し、就寝します。装置が一定の空気圧で空気を送り込むことで、気道の閉塞を防ぎ、安定した呼吸を維持することができます。
CPAP(持続陽圧呼吸療法)は、睡眠時無呼吸症候群の治療で最も一般的な方法です。装置から伸びるホースの先に取り付けられたマスクを装着し、就寝します。装置が一定の空気圧で空気を送り込むことで、気道の閉塞を防ぎ、安定した呼吸を維持することができます。
マウスピース療法
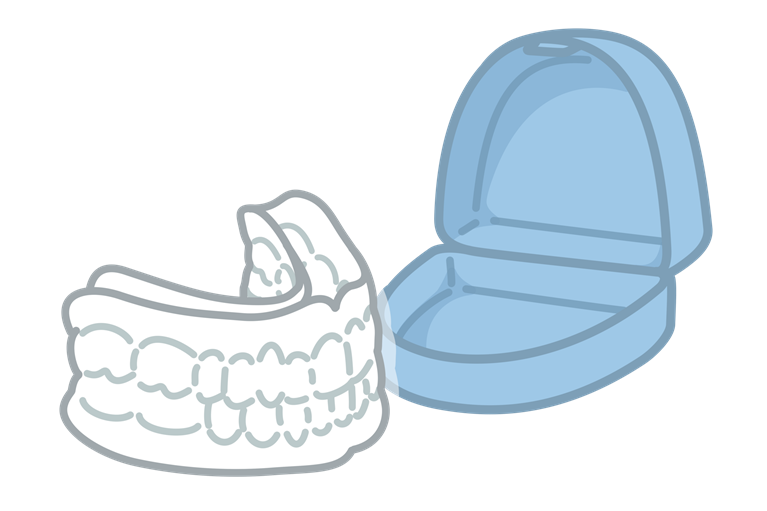 歯科で型取りをして、特殊なマウスピースを作成し、就寝時に装着します。特殊な形状をしており、装着によって下顎が前方で固定されます。これにより、気道を確保しやすくなります。マウスピースを使った治療が必要になった場合には、歯科を受診していただきます。
歯科で型取りをして、特殊なマウスピースを作成し、就寝時に装着します。特殊な形状をしており、装着によって下顎が前方で固定されます。これにより、気道を確保しやすくなります。マウスピースを使った治療が必要になった場合には、歯科を受診していただきます。
手術
扁桃肥大、アデノイド肥大を原因として起こる睡眠時無呼吸症候群の場合には、手術を検討します。手術が必要になった場合には、提携する基幹病院をご紹介します。
生活習慣の改善
肥満、寝酒、喫煙などに原因がある場合には、生活習慣を改善し、睡眠時無呼吸症候群の根本的な治療を目指します。肥満の方には、食事療法・運動療法を組み合わせた、無理のないダイエット指導を行います。
睡眠時無呼吸症候群を
放っておくとどうなる?
睡眠時無呼吸症候群を放置していると、以下のようなリスクが発生したり、増大したりします。単なる「いびきをかく病気」と軽く見ず、お早めに当院にご相談ください。
高血圧の原因になり、
心臓への負担がかかる
無呼吸の状態から呼吸が再開される際、脳が一時的に目覚め、交感神経が優位になることで血圧が上昇します。このような血圧の上昇を夜中に何度も繰り返し、またそれが毎日続くと、心臓への負担が大きくなり、心筋梗塞や狭心症などのリスクが高まります。
交通事故のリスク
睡眠時無呼吸症候群の日中の代表的な症状に、強い眠気があります。また、集中力の低下、倦怠感といった症状も見られます。これにより、車の運転中の居眠り、交通事故が懸念されます。ある調査によると、睡眠時無呼吸症候群の方はそうでない方よりも交通事故を起こすリスクが7倍になると報告されています。車で通勤をする人、営業などでよく車を運転する人などは、特にお早目の受診をおすすめします。
糖尿病を合併しやすくなる
睡眠時無呼吸症候群によって睡眠の質が低下すると、交感神経が活性化し、血糖値や血圧が上昇します。加えて、成長ホルモンの分泌の低下による筋肉の減少・脂肪の増加が起こり、インスリンの効きが悪くなります。その結果として、糖尿病を合併しやすくなります。またすでに糖尿病を発症している方は、その悪化が懸念されます。